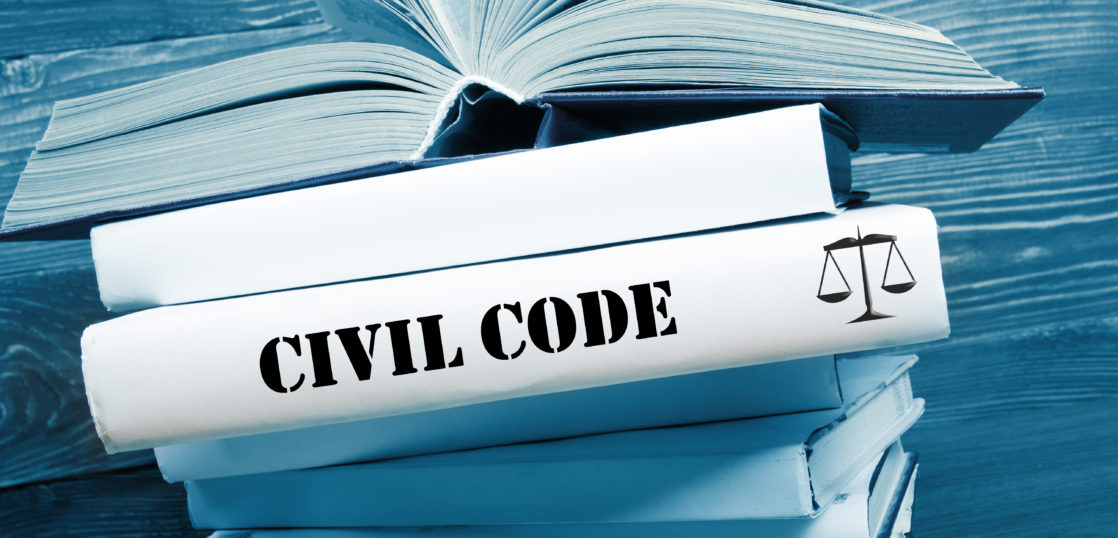2020年4月1日より、改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正)された民法(以下「改正民法」といい、改正される前の民法を「改正前民法」といいます。)が施行されました。今回の民法改正は、1896年に制定された後、約120年間もの間ほとんど改正がなされてこなかった法律を、社会・経済の変化への対応を図ること及び実務においては一般的となっているルールを適切に明文化することを目的として、改正するものであり、その変更点は非常に広範囲にわたっています。本記事では、このような改正のうち、資金調達等において重要な役割を果たすことが期待されている債権譲渡に関する法制度の主要な変更点を解説した上で、債権譲渡による資金調達等を円滑化する法制度について補足的に解説していきたいと思います。
目次
1. 民法改正における債権譲渡に関する法制度の主要な変更点
(1) 譲渡禁止特約に反する債権譲渡
(a) 譲渡禁止特約に反する債権譲渡の効力
まず、改正前民法において、債権譲渡に関する法制度はどのようなものだったのでしょうか。
改正前民法第466条第1項は、債権譲渡自由の原則(当該債権の性質が債権譲渡に適さない場合を除いて、債権を自由に譲渡することができる。)を定め、同条第2項は、当事者が反対の意思表示をした場合(以下「譲渡禁止特約」といいます。)には同原則を適用しない旨を定めていました。そこで、譲渡禁止特約が付された債権の譲渡は無効になるものの、譲渡禁止特約について善意・無重過失の譲受人に対しては、譲渡禁止特約の存在を主張することができないものと解されていました(物権的効力説、改正前民法第466条第2項)。
上記解釈は、譲受人が善意・無重過失であるかという主観により債権譲渡の有効・無効が決まってしまう点において、債権譲渡に係る取引の安定性を欠くことになると批判されてきました。また、上記解釈は、債権譲渡が、弁済期前に債権を売り渡して代金を得ることや、債権を担保に供して融資を受けること等を目的として行われ、特に中小企業において、効果的な資金調達手段として機能することが期待されているにもかかわらず、中小企業の資金調達等を妨げることになるといった問題点が指摘されていました。
そこで、改正民法は、債権譲渡による資金調達等を円滑化するために、譲渡禁止特約が付されていても、これによって債権譲渡の効力が妨げられないことを明記しました(改正民法第466条第2項)。
そして、譲渡禁止特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は、債務の履行を拒むこと及び譲渡人に対する弁済等を譲受人に対抗することができるものと規定することで、債務者の弁済先を固定する利益(以下「弁済先固定利益」といいます。)を一定程度保護することとしました(改正民法第466条第3項)。なお、ここでいう弁済先固定利益とは、債務の弁済の相手方を固定することで得られる、事務の煩雑化や誤弁済のリスクを回避する債務者の利益を意味します。このように改正民法の下では、譲受人の主観にかかわらず債権譲渡は有効に成立するとして資金調達等を促進する一方、債務者の弁済先固定利益を引き続き一定の場合に保護することで、両者の利益の調和が図られました。
上述した譲渡禁止特約に反する債権譲渡の効力に関する民法改正の影響は、具体的には、以下のような場面において、現れるものと考えられます。
① 債権の転得者が現れた場合
改正前民法下では、債権の直接の譲受人が悪意であっても、当該譲受人から債権を譲り受けた転得者が善意である場合には、債務者は、転得者に譲渡禁止特約を対抗することができず、善意の転得者は当該債権を有効に取得することができるものと解されていました。また、直接の譲受人が善意であった場合には、その後に悪意の転得者が現れたとしても譲渡禁止特約の対抗を受けないとする考え方(絶対的構成)と、転得者が悪意であれば当該転得者には譲渡禁止特約が適用されるとする考え方(相対的構成)の対立がありました。
しかしながら、改正民法下では、絶対的構成及び相対的構成のいずれの考え方も採用せず、譲受人や転得者の主観にかかわらず、債権は譲受人又は転得者に有効に帰属することとしたうえで、譲受人又は転得者の主観によって、債務者の弁済先固定利益が保護されるか否かが決まるという考え方を採用しました。
② 債権が二重に譲渡された場合
譲渡禁止特約の付された債権が二重に譲渡された場合、改正前民法下では、いずれの債権譲渡が優先するものであるかを決める第三者対抗要件具備の先後について確認する前に、債権譲渡が有効であるかを判断するために、譲受人の主観を問題とする必要がありました。
しかし、改正民法下では、債権は譲受人双方に帰属することになりますので、第三者対抗要件を具備した時期の先後によって、どちらの債権者が優先するか判断されることになります。
③ 担保権の設定
改正前民法下では、譲受人の主観によって債権譲渡の有効性が左右されてしまうため、譲渡禁止特約の付された債権が担保提供されることは多くありませんでした。
しかしながら、改正民法下では、譲渡禁止特約が付されていたとしても、有効に債権譲渡担保契約を締結することができるようになりました。これにより、売掛代金債権等を担保とした資金調達がより一層活発化するのではないかと思われます。なお、預貯金債権について別途の取扱いがされていることについては、下記1(1)(d)で後述します。
その他、改正前民法と改正民法とでは、上記のとおり、原則と例外が逆転されているため、裁判における主張立証という観点からは、改正民法の下では、譲受人の悪意・重過失につき債務者が立証責任を負うものと解釈される点について、債務者は注意する必要があります。
(b) 譲渡禁止特約に反する債権譲渡について悪意・重過失の譲受人が取るべき対応
改正民法の下では、悪意・重過失の譲受人は、債務者に履行を拒まれた場合には、相当の期間を定めて譲渡人へ履行するよう債務者に催告して、債務の履行をさせることができます(改正民法第466条第3項)。この場合において、債務者が譲渡人に債務の履行を行ったときは、債権譲渡自体は有効に成立しているため、当該債務の履行については、譲渡人・譲受人間の債権譲渡契約において関連する条項が定められている場合には当該条項に従って、又は不当利得返還請求によって精算されることとなります。
一方で、相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず当該期間内に債務者による債務の履行がない場合は、債務者の弁済先固定利益は保護されないものとなり、譲受人は、譲渡禁止特約について悪意又は重過失であったとしても、当該債務者に対して自らに対する債務の履行を求めることができます(改正民法第466条第4項)。
なお、債務者が譲受人に対して対抗できるのは債権譲渡に係る対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由に限定されるのが原則ですが(改正民法第468条第1項)、このように債務者が譲受人に対して債務を履行する義務が発生する場合には、かかる原則が修正され、上記催告期間を経過したときまでに譲渡人に生じた事由(譲渡債権の不成立、取消・解除等による債権の消滅等に係る既発生の抗弁や抗弁権発生の基礎となる事実を含みます。)をもって、債務者が、譲受人に対抗することができるとされている点に留意が必要です(改正民法第468条第2項)。
(c) 譲渡禁止特約に反する債権譲渡の契約上の責任
上述したとおり、改正民法の下では、譲渡禁止特約が付されている場合にも、債権譲渡を有効に行うことができるようになりました。
しかしながら、譲渡禁止特約が付されている以上、当該債権譲渡は、譲渡禁止特約の規定された契約に違反することになるため、当該契約の解除事由に該当したり損害賠償の対象となるのでしょうか。
この点については、改正民法の下でも、債務者は、譲渡人に対して弁済等をすれば免責される等(改正民法第466条第3項参照)、弁済の相手方を固定することへの債務者の期待は一定程度保護されているため、譲渡禁止特約が弁済の相手方を固定する目的でなされた場合は、資金調達等を目的とした債権譲渡は形式的には同特約に違反するとしても、必ずしも同特約の趣旨に反するとは言えないと考えることができ、契約違反にはならないものと解釈されています。
また、譲渡禁止特約に反する債権譲渡がなされたとしても、債務者にとって特段の不利益はないため、当該債権譲渡が譲渡禁止特約違反であることを理由に取引の打切りや契約の解除を行うことは、極めて合理性に乏しい行為であるといえ、権利濫用等に当たり得るものとも解釈されています。
但し、上記はあくまで解釈論にすぎず、明文や確立された判例法理が存在しないため、契約当事者としては、自らの利益を守るためには、自らの意向を契約書に明記しておくべきでしょう。
具体的には、譲渡禁止特約に反する債権譲渡を行う場合には事前に譲受人に対し譲渡禁止特約が付されていることを告知する義務を規定するとともに(それにより譲受人が譲渡禁止特約について悪意となり、改正民法第466条第3項に基づき弁済先固定利益が保護されることになります。)、告知をしたうえでの債権譲渡は、譲渡対象となる契約の違反にはならないことを明記することが考えられます。このように告知義務が規定された場合で債権者が当該義務に違反したときには、債務不履行として、契約の解除事由に該当したり損害賠償の対象になるでしょう。
なお、弁済先固定利益だけではなく、債権者が変更されないことが重要とされる場合も考えられます。例えば、債権者が適格機関投資家等の一定の要件を満たしている者でなければ債務者が不利益を被る場合(例:租税特別措置法の要件を満たさなくなってしまう場合)、弁済先を固定するだけではなく、債権者を固定したいという債務者側の合理的な要請があります。このようなケースには、譲渡禁止特約に違反した場合には債務不履行となり、解除事由に該当し損害の賠償責任が発生するということを契約書に明記しておくべきでしょう。
(d) 預貯金債権の譲渡
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」といいます。)については、その他の債権と取扱いが異なっており、改正民法の下においても、譲受人が譲渡禁止特約について悪意・重過失の場合には債権譲渡は無効となります(改正民法第466条の5第1項)。
預貯金債権は、譲渡禁止特約が付されているのが周知の事実であり、銀行は預貯金債権が譲渡されない前提で管理をしており、自由な譲渡を認めた場合には銀行に多大な管理コストが発生する可能性があること、預貯金債権は頻繁に入出金が行われるため銀行の円滑な払戻し業務に支障が生じる可能性があること及び実務上預貯金債権の譲渡は頻繁に行われるものではないこと等が異なる取扱いの理由として考えられます。
(2) 将来債権の譲渡
改正前民法の下では、将来発生すべき債権(以下「将来債権」といいます。)の譲渡に関する規定は存在しておらず、これについても資金調達等を目的とする債権譲渡を円滑化するために明確な法律規定が必要であるとの指摘がなされてきました。
そこで、改正民法は、将来債権の譲渡の有効性、譲受人が将来債権を取得する時期及び第三者対抗要件の具備等についての判例法理(最三小判平成11年1月29日民集53巻1号151頁等)を具体化し、以下の点を明記しました(改正民法第466条の6及び同法467条)。
① 将来債権を譲渡することが可能であること(改正民法第466条の6第1項)
② 当該将来債権の発生時に譲受人が当然に当該将来債権を取得すること(改正民法第466条の6第2項)
③ 第三者対抗要件は現在債権と同様に確定日付のある証書による債務者への通知又は債務者の承諾であること(改正民法第467条)
将来債権が譲渡される場合には、債権譲渡契約を締結した後に譲渡禁止特約が付される可能性があるため、対抗要件具備時までに譲渡禁止特約が付されたときは、譲受人は悪意であるとみなされるものとされており、その場合には、上記1(1)記載の悪意・重過失の譲受人に対する法規制が適用される点に留意する必要があります(改正民法第466条の6第3項)。
(3) 債権譲渡における相殺
改正前民法の下では、債務者が譲渡の通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって債権の譲受人に対抗することができると規定されているだけで(改正前民法第468条第2項)、債権譲渡の際に債務者が譲渡人に対する反対債権を持っていた場合等において、譲受人に対して相殺権を行使するための要件は明確に規定されておらず、解釈論及び判例法理(最一判昭和50年12月8日民集29巻11号1864頁等)に委ねられていました。具体的には、(a)相殺をする者にとっての債権である自働債権及び債務である受働債権の弁済期の先後等によって相殺に制限を加えるべきか否か、(b)債権譲渡の対抗要件具備時点で相殺適状(相殺をするために必要とされる一般的な要件を満たしている状態(改正民法第505条第1項))であることが必要なのか、(c)債権譲渡の対抗要件具備時点で相殺適状であることが必要でないとしても、その時点で相殺の期待が成立しているだけでよいのか、(d)相殺の期待だけでよいとするとどのような場合に相殺の期待が成立しているといえるのかといったことが議論されてきました。判例法理は、(a)の点について、自働債権が対抗要件を具備する前に取得されたものである限り、自働債権の弁済期が到来して相殺適状に達すれば、対抗要件を具備した後でも債務者は相殺をすることができるとする無制限説を採用したようでしたが、事例判決にすぎないと理解されており、一般的な要件の明確化が望まれていました。
そこで、改正民法は、明記されていなかった相殺に関する論点を整理し、債務者が以下の債権を譲渡人に対して有している場合に、当該債権と譲渡債権の相殺を譲受人に対抗できる旨明記しました。
① 債権譲渡の対抗要件具備時より前に取得した債権(改正民法第469条第1項)
② 債権譲渡の対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権で、対抗要件具備時より後に取得した債権(同条第2項第1号)
③ ②のほか、譲渡債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権で、対抗要件具備時より後に取得した債権(同項第2号)
まず、①においては、債権譲渡の対抗要件を具備した時よりも前に取得した債権を自働債権とする相殺を認めています。そして、②においては、債権譲渡の対抗要件を具備した時より後に債権を取得した場合であっても、当該債権が対抗要件を具備した時よりも前の原因に基づいて発生したものであるならば、当該債権の発生原因の時点において相殺の期待が生じていたとして、当該債権を自働債権として相殺を許容することとされています。最後に、③においては、債権譲渡の対抗要件を具備した時より後に債権を取得した場合であっても、当該債権が譲渡債権の発生原因である契約に基づいて生じたものであるならば、当該契約の締結の時点において相殺の期待が生じていたとして、当該債権を自働債権として相殺を許容することとされています。上記①乃至③のいずれのケースでも、対抗要件具備時に相殺適状にあることが要求されておらず、自働債権と受働債権の弁済期の先後関係について何ら制限が設けられておりません。また、②及び③においては、どのような場合に相殺の期待を保護するかが明らかにされております。
なお、②と③の違いが解りづらいと思いますので補足説明します。
③は、譲渡債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権のうち、②に該当するもの以外(すなわち、債権譲渡の対抗要件具備時より後の原因に基づいて生じた債権)です。具体的な事例としては、将来締結される製品売買契約に基づく売買代金債権が譲渡された場合が挙げられます。この場合、製品売買契約締結前に債権譲渡及び対抗要件具備が行われ、その後、製品売買契約が締結されそれに基づき売買代金債権が発生した時点で債権譲渡の効力が発生します(改正民法466条の6第2項)。このケースにおいて、売買契約の目的物の契約不適合を理由として買主(譲渡債権の債務者)が損害賠償請求権を有することとなった場合に、債権譲渡の対抗要件具備時より後の原因に基づいて生じた債権だからという理由で当該損害賠償請求権を自働債権とする相殺が認められないとすると買主に酷です。このようなケースにおいて、譲渡債権の債務者の相殺への期待を保護するというのが、民法第469条第2項第2号の趣旨です。このように、③の改正民法第469条第2項第2号は、対抗要件を具備した後の原因に基づいて生じた債権であって、また、その発生原因が譲受人の取得する債権を発生させる契約と同一の契約であるものを自働債権とする相殺について規定するものであるため、受働債権を発生させる原因である契約も対抗要件を具備した後に締結されたことが前提となっております。従って、改正民法第469条第2項第2号は、将来債権が譲渡された場合に限って適用されることになるものと考えられています。
このように改正民法では相殺の要件について明確化されました。譲受人は、債権を譲り受ける際に、上記各規定に基づいて債務者から相殺の主張をされる可能性があるか慎重に検討する必要があります。将来債権を譲り受ける際には特に注意が必要です。例えば、金融機関が将来債権に譲渡担保を設定する場合には、関連する融資契約や担保契約において、譲渡債権の発生原因である契約に債務者からの相殺を禁止する規定を盛り込むことを譲渡人(借入人)の義務とする等の対応が考えられます。
(4) 経過規定
上述した債権譲渡に関する改正民法の各規定は、改正民法の施行日以後に債権譲渡の原因となる法律行為がされた場合に適用されます(民法附則(平成29年法律第44号)第22条)。
従って、譲渡する債権の発生日や債権譲渡の効力発生日等が基準になるわけではなく、債権譲渡契約を締結した日が基準となる点に留意する必要があります。
2. その他の債権譲渡による資金調達を円滑化する法制度
上述した民法改正は、債権譲渡による資金調達等を円滑化する目的に基づいていますが、その他の法令等においても、同様の趣旨に基づく規定が設けられています。
下請中小企業の振興を図るために、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められた振興基準(以下「振興基準」といいます。)第8条第5項には、2016年12月14日付改正によって以下の規定が設けられており、①親事業者と下請事業者の間で債権譲渡禁止特約を付する場合であっても、金融機関等に対する債権譲渡・担保提供は禁じない内容とするよう努めるものと規定するとともに、親事業者に対し、②下請事業者による譲渡禁止特約の解除要請への配慮、③譲渡承諾への協力を求めるなど、下請事業者による資金調達等に対する一層の配慮が求められています。
① 親事業者は、下請事業者との間での基本契約の締結の際に債権譲渡禁止特約を締結する場合であっても、信用保証協会、預金保険法(昭和46年法律第34号)に規定する金融機関等及び親事業者と下請事業者の双方で確認した適切な相手先に対しては、譲渡又は担保提供を禁じない内容とするよう努めるものとする(振興基準第8条第5項第1号)。
② 親事業者は、下請事業者から、報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡又は担保提供のために、基本契約等において締結された債権譲渡禁止特約の解除の申出があった場合には、申出を十分尊重して対応するとともに、本申出を理由として不当に取引の条件又は実施について不利な取扱いをしてはならないものとする(振興基準第8条第5項第2号)。
③ 親事業者は、禁止特約を解除していない場合であっても、下請事業者からの要請に応じ、報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡の承諾(対抗要件の具備)に適切に努めるものとする(振興基準第8条第5項第3号)。
上述した振興基準に定める事項については、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)より、下請事業者又は親事業者に対して行政指導がなされることが考えられるため、親事業者としては、下請事業者との間で譲渡禁止特約付の契約を締結する場合には、改正された民法に加えて、振興基準にも留意して契約交渉を進める必要があるでしょう。
3. さいごに
以上のとおり、本記事では、民法改正における債権譲渡に関する法制度の主要な変更点、下請中小企業振興法による下請業者の資金調達の円滑化のための制度を解説いたしました。債権譲渡は、資金調達をするうえで簡易で非常に有用な手段であり、今回の民法改正によって取引の安定性も高められました。本記事においてご説明しました留意点に注意していただいたうえで、債権譲渡による資金調達等について積極的にご検討いただければ幸いです。
なお、改正前民法の下で債権譲渡を行う際に、一般的に行われていた債務者からの異議なき承諾(改正前民法第468条第1項)の取得については、改正民法において制度の変更がありました。この点については、別の記事にて解説させていただきます。
本記事のトピックその他民法改正や債権譲渡に関連するお問い合わせは、以下のボタンから問い合わせフォームを通じてご連絡ください。